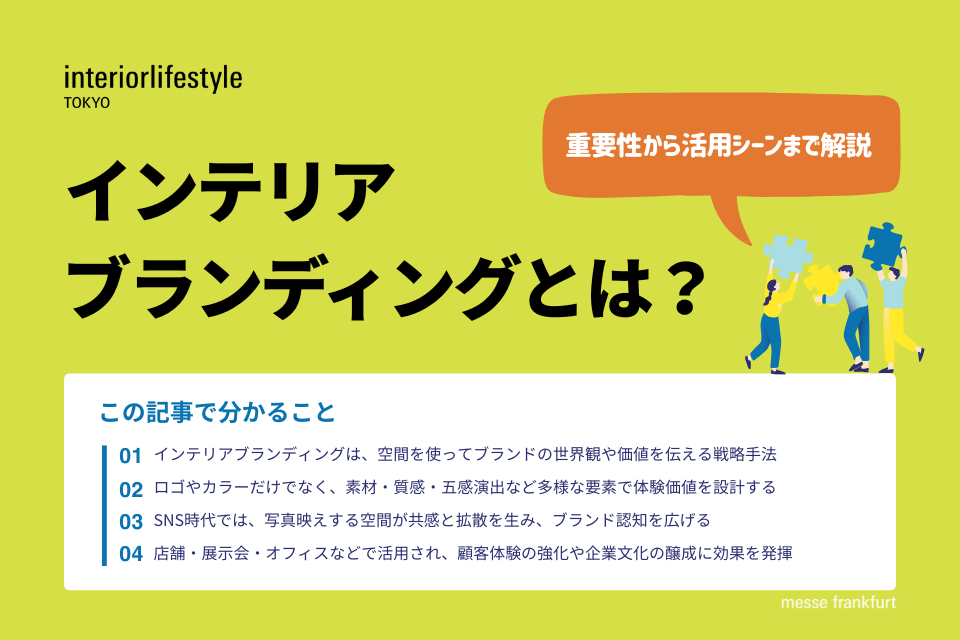本記事ではインテリアブランディングに関する情報を紹介します。インテリアブランディングとは?から、インテリアブランディングの重要性、活用シーンまで徹底解説します。インテリアブランディングについて知りたい方はぜひ本記事を参考にしてください。
インテリアブランディングとは?|重要性から活用シーンまで解説
「インテリア 集客」というキーワードは、近年競争が激化する家具・インテリア市場において、ますます重要性を増しています。
多様化する販路や情報過多なデジタル環境の中で、認知拡大や購買促進において従来の施策だけでは成果を出しづらくなっています。
特に、BtoB領域においてはSNSやECのみでは不十分であり、リアルな場でのブランディングや商談機会の創出が新たな課題となっています。
本記事では、インテリア業界における集客の現状とその課題を明らかにしながら、見本市出展というリアルな手法の有効性について具体的に解説します。
複数の集客手段を比較しながら、業界関係者が検討すべきアプローチを論理的に提示します。
▼この記事で分かること ● インテリア業界における集客の現状と課題 ● 主要な集客手法の特徴と限界 ● 見本市出展による集客のメリット・デメリット ● ブランド価値を伝える手段として見本市が有効な理由 |
インテリア業界の現状
家具・インテリア業界は、消費者のライフスタイル変化や経済環境の影響を強く受けます。
需要は一定数存在しているものの、かつてのような拡大基調にはなく、各ブランドは差別化のための新しい集客施策が必要です。
特に、店舗・EC双方における来客数やアクセス数の頭打ちが見られ、効果的な手段を求める声が増えています。
▼インテリア業界の現状2つ
● インテリア需要の伸び悩み ● ブランド増加による競争の激化 |
インテリア需要の伸び悩み
インテリア需要は安定はしているものの、伸びは限定的です。
少子高齢化による世帯数の減少・住宅購入や引っ越し件数の停滞・サブスク家具やリユース市場の拡大などが主な理由です。
これらの要因により、新規顧客の獲得スピードが鈍化しています。
良い例として、賃貸層向けに小型・低価格の家具を展開する企業は一定の成果を出しています。
一方で、従来通り大型家具に依存しているメーカーは売上の伸び悩みに直面しています。
現状を踏まえると、単なる広告施策に頼るのではなく、ターゲットに沿った明確な導線づくりが不可欠です。
具体案として、購買動機が高まるタイミング(引越し・結婚・リフォームなど)を捉えた集客戦略を立てることが有効です。
ブランド増加による競争の激化
ブランド数の増加により、競争の激化が進んでいることも売上の伸び悩みの要因です。
新規ブランドが毎年参入し、既存企業との差別化が難しくなっています。
小規模ブランドでも、SNSやECを活用することで参入が容易になったことや、海外ブランドの日本市場参入などが主な理由です。
そのため、自社の強みを明確に定義し、それを体験として伝えられる施策を検討することの必要性が大きくなっています。
単なる商品訴求ではなく、生活シーンや世界観を伝えることが、競合に埋もれない施策と言えるでしょう。
インテリア業界の課題
インテリアブランディングは、空間のデザインだけで成り立つものではありません。
ブランドの核となる思想や、ロゴ・カラーといった視覚的要素、さらには素材選定や照明、といった、多様な要素が組み合わさることで完成されます。
ここでは、ブランディングにおいて重要な構成要素を一つずつ解説します。
▼インテリアブランディングの要素
● ブランド価値の可視化 ● SNS・共感時代の世界観設計の強化 ● リアル空間での差別化・記憶化 |
ブランド価値の可視化
インテリアブランディングの大きな役割のひとつは、言語化が難しいブランドの価値観や方向性を「視覚」で伝えることです。
ロゴやタグラインといった表面的な要素だけでは、ブランドの真意は伝わりにくい場面もあります。
そこで、空間という三次元の場を活用すれば、ユーザーの直感に訴えかける事が可能です。
照明、家具、導線設計といった構成要素を通じて、ブランドのトーンや温度感まで伝えられます。
例えば、高級志向のブランドであれば、静寂感や質感にこだわった空間設計を行うことで、視覚情報からラグジュアリーさを伝えられます。
このように、空間のデザインそのもので、ブランドのコンセプトを語ることが可能です。
SNS・共感時代の世界観設計の強化
現在のマーケティングにおいて、「共感」は重要なキーワードです。特にSNSでは、共感できるストーリーや世界観があれば、ユーザーに拡散されやすいです。
インテリアブランディングは、こうしたSNS時代の文脈にも対応します。写真映えするビジュアルや、コンセプトに一貫性のある空間は、ユーザーによる自発的なシェアを促します。
さらに、オフラインとオンラインの接点をつなぐ導線にもなりえます。リアルな体験をSNSに載せてもらうことで、非来店者にもブランドの世界観を間接的に伝えることが可能です。
リアル空間での差別化・記憶化
商品やサービスがコモディティ化しやすい現在、競合との差別化は困難になりつつあります。そこで重要なのが「体験価値の設計」です。
空間を通じたブランディングは、その有効な手段のひとつです。
特に展示会や店舗などでは、数秒で興味を引かなければ素通りされてしまいます。空間の第一印象によってブランドへの注目度が変わるため、一瞬で伝える仕掛けが必要です。
また、ユーザーの記憶に残すためには、五感を刺激する演出や、ストーリー性のある構成が効果的です。単なる情報提示ではなく、訪問そのものが印象的な体験となるような空間作りが求められています。
インテリアブランディングを構成する要素
インテリアブランディングは、空間のデザインだけで成り立つものではありません。
ブランドの核となる思想や、ロゴ・カラーといった視覚的要素、さらには素材選定や照明、香り、音といった五感に訴える演出まで、多様な要素が組み合わさることで完成されます。
ここでは、ブランディングにおいて重要な構成要素を一つずつ解説します。
要素①|ビジョンの視覚化
ブランドの思想や未来像を明確に伝えるためには、空間全体がそのビジョンを反映する必要があります。
ただ美しい空間をつくるだけでは、ブランドの本質は顧客に届きません。コンセプトのない設計は、単なる装飾にとどまってしまいます。
ビジョンの視覚化とは、ブランドが何を目指し、どんな社会価値を提供しようとしているかを、視覚的要素や構造、設計思想に落とし込む作業です。
例えば、「サステナブルな社会を目指す」という理念を持つ企業であれば、再生素材や自然光を取り入れた空間構成によって、理念をデザインに反映させることができます。
このアプローチは、来訪者にブランドの意図を無言で伝える手段として非常に効果的です。
説明的な掲示やパンフレットに頼らなくても、空間の体験を通じて企業の姿勢が伝わるようになります。
要素②|カラー・ロゴとの連動性
ブランドを象徴するロゴやキーカラーは、空間演出においても中核的な役割を果たします。
デジタルや広告媒体で定着したビジュアルアイデンティティが、リアル空間でも一貫しているかどうかは、顧客体験の質に直結します。
例えば、ロゴに使用されている赤が印象的なブランドであれば、空間の差し色やアクセントにも同系色を採用することで、ビジュアル上の統一感を保てます。
また、フォントの選び方やサインデザインにまで気を配ることで、空間とグラフィックの整合性が保たれ、ブランドへの信頼感も高めることが可能です。
一方で、ロゴやカラーを強調しすぎると広告的・装飾的に見えてしまう恐れがあります。ブランドの世界観と融合させた自然な演出を目指すことが重要です。
視覚的な要素は、認識の早さと記憶の定着に強く影響を及ぼすため、空間全体との調和が求められます。
要素③|素材・質感による価値観の表現
インテリアにおける素材選びは、空間の物理的な質感だけでなく、ブランドの価値観や姿勢も表現する要素です。
木材や石、金属などのマテリアルは、それぞれ異なるメッセージ性を持っており、その選定が空間に込める思想と直結します。
例えば、ナチュラル志向のブランドであれば、無垢材やリネンといった自然素材が好まれます。
質感は、見た目以上に「手触り」や「触れてみた印象」によってブランドイメージに影響を与えます。
無機質な空間よりも、温度を感じさせる素材を活用することで、ブランドへの親しみや安心感を演出可能です。
視覚だけに頼らず、素材そのものが語る力を活かすことが、深いブランディングに繋がります。
要素④|五感を活用した空間演出
ブランド体験を深めるためには、視覚だけでなく、聴覚・嗅覚・触覚・味覚といった五感に訴える空間設計が有効です。
特にリアルな場では、オンラインでは再現できない「体感」がブランドの差別化に直結します。
例えば、店舗でのBGM選定や香りの演出は、空間全体の雰囲気を左右します。特定の音や香りは記憶と強く結びつくため、リピート来店やSNS投稿時に「あの空間」として記憶に残りやすいです。
視覚的な印象に比べて定着率が高いとされており、ブランディングにおいて重要な役割を果たせます。
さらに、導線や動線の中で触れる素材、足裏に伝わる床材の感触なども、ユーザー体験の質を左右します。
感覚的な体験を重視する設計は、ブランドとのエンゲージメントを長期的に築く基盤になります。
インテリアブランディングの進め方
インテリアブランディングは、単なるデザインプロセスではありません。
ブランドの本質を捉え、空間という形で体現するためには、段階的な設計と実装の流れが不可欠です。
ここでは、戦略的かつ実践的な観点から、インテリアブランディングの基本ステップを3段階に分けて解説します。
▼インテリアブランディングの進め方
● ステップ①|ブランドの核となるコンセプトを明確にする ● ステップ②|空間コンセプトを設計し、素材・色・構成要素を決める ● ステップ③|デザイン・施工・実装を行う |
ステップ①|ブランドの核となるコンセプトを明確にする
インテリアブランディングの出発点は、「なぜこの空間が存在するのか」を定義することです。
ブランドが提供する価値、社会的意義、顧客との関係性、すべてを支えるコンセプトを明確に言語化することで、以後のすべてのデザイン・選定に統一性が生まれます。
ここで重要なのは、見た目の好みやトレンドではなく、ブランドらしさを定義することです。
表面的なデザインの好みではなく、企業が社会や顧客に対してどのような立場を取り、どのような未来を描いているのかを言語化する作業です。
また、社内外に向けたメッセージ性を意識することも大切です。
内部向けには企業文化の醸成や従業員のモチベーションアップに繋がり、外部向けにはブランドの理念やビジョンを体験として届ける手段です。
ステップ②|空間コンセプトを設計し、素材・色・構成要素を決める
ブランドの核が定まったら、それを空間に落とし込みます。
このステップでは、どのような物理的要素を使ってブランドのコンセプトを視覚化・体感化するかを設計します。
空間のレイアウトや動線計画、天井高、光の取り入れ方などはもちろん、素材やカラー、壁面グラフィックに至るまで、空間に関わる全要素がブランドの一部として機能します。
例えば「開放感」を打ち出したい場合は、余白を多く取り、自然光を多く取り入れるような設計が必要です。
ここで気をつけるのは、ブランドコンセプトとデザインの一貫性です。
表現の方向性がブレると、顧客に意図が伝わらず、印象に残りません。社内で複数の関係者がプロジェクトに関わる場合は、空間コンセプトシートなどを用いて、共通認識をつくることも効果的です。
ステップ③|デザイン・施工・実装を行う
最終ステップは、設計された空間コンセプトを実際の空間として実装する段階です。
ここでは、デザイナー、施工業者、什器メーカー、照明・音響など、複数の専門業者との連携が必要となります。
施工段階では、設計図と実際の仕上がりに差異が出ることもあるため、ディレクションや現場管理が非常に重要です。
ブランドイメージの齟齬を防ぐためには、設計意図を明確に伝える図面や資料、サンプルなどを用意し、プロジェクトメンバー間の共通理解を徹底する必要があります。
また、施工後に「どう活用されるか」を視野に入れた設計も欠かせません。
導線や照明の具合など、実際の利用シーンを想定したうえでの最終調整も必ず行いましょう。必要に応じて、プレオープン期間を設けて検証することも効果的です。
インテリアブランディングの活用シーン
インテリアブランディングは、業種や業態を問わずさまざまな場面で応用が可能です。
特に「顧客との接点が生まれる空間」では、ブランドの世界観を体験として届けられるため、効果が顕著に表れます。
このセクションでは、活用が進む3つの代表的な空間における具体的な活用イメージを紹介します。
▼インテリアブランディングの活用シーン
● シーン①|店舗・ショールームなどの商業空間 ● シーン②|展示会・ポップアップ・イベント空間 ● シーン③|オフィス・ワークスペースのブランディング |
シーン①|店舗・ショールームなどの商業空間
実店舗は、ブランドが顧客と直接つながる貴重なタッチポイントです。
単なる物販や接客の場ではなく、ブランド体験を提供する場の役割を担います。そのため、空間にブランドらしさを反映させることが重要です。
例えば、同じ商品を扱っていても、店内の内装や照明、什器の配置などで、顧客に与える印象は大きく異なります。
顧客の購買行動は、価格や機能だけではなく、体験によっても大きく左右されます。
ショールームにおいても、製品単体では伝わりにくいブランドの世界観や価値観を、空間全体で表現することで理解を深められます。
シーン②|展示会・ポップアップ・イベント空間
展示会やイベント、ポップアップショップなどの一時的な空間でも、インテリアブランディングの力は大きな差を生みます。
限られた時間とスペースで自社のブランドを伝えるためには、空間全体で伝わる工夫が必要です。
例えば、展示会場では数百社が同時に出展することもあります。そのなかで、自社のブースが他と差別化され、訪問者の足を止めるためには、視覚的なインパクトとコンセプトの一貫性が求められます。空間設計におけるブランディングが、集客効果と認知拡大に重要です。
また、SNS上での発信を促すためには、フォトジェニックなスポットやハッシュタグ訴求を組み込んだ設計も効果的です。実際に来場者が写真を投稿することで、リアルの接点がオンラインにも拡張され、短期間でも大きなブランド波及効果が見込めます。
さらにポップアップの場合は、ブランドの世界観を短時間で伝える必要があります。
空間の完成度がそのままブランドの信頼感に直結するため、設計段階から綿密なストーリー設計とビジュアル統一が重要です。
シーン③|オフィス・ワークスペースのブランディング
オフィスもまた、ブランドを体現する重要な空間です。
特に採用活動や取引先の訪問など、社外の目に触れる場面では、空間がブランドの印象形成に大きく関与します。
また、社内向けにも効果があります。働く社員がブランドの理念を日常的に体感できるようにすることで、組織文化や従業員エンゲージメントの向上につながります。
単なる働く場所ではなく、ブランドと過ごす空間として設計することで、社員が自社に誇りを持ちやすくなります。
例えば、企業理念やビジョンに基づいたアートワークやサイン計画を導入すれば、日常のなかで自然とブランドの方向性に触れることが可能です。
また、レイアウトや素材選びによって、心理的安全性や創造性を促進するような空間を作れます。
オフィス空間のブランディングは、社外への発信と社内文化の形成を同時に実現できる戦略的手法です。
まとめ
インテリアブランディングは、単なる空間演出ではありません。
ブランドの核を体現し、顧客に「体験としての価値」を届けるための、極めて戦略的な手段です。ロゴや商品だけでは伝えきれないブランドの思想や世界観を、リアルな空間を通して表現することで、より深い共感や記憶に残る関係性を築くことができます。
特に、D2Cブランドやライフスタイル系の企業にとっては、SNS映えやストーリー性が重視されるため、インテリアブランディングの有効性はさらに高まっています。
一方、「どこから始めればいいか分からない」「デザインとブランディングの整合性が取りにくい」といった悩みを抱える企業も少なくありません。
だからこそ、インテリアブランディングはブランド戦略全体の中で設計し、空間・グラフィック・コンテンツを一貫してプロデュースする必要があります。
メッセフランクフルトはドイツ・フランクフルト市に本社を構え、世界最大級の見本市会場の運営と国際見本市を主催しています。800年にわたる歴史を誇り、世界28ヵ国・地域で事業を展開しています。
メッセフランクフルト ジャパンは、メッセフランクフルトの日本支社としてグローバルなネットワークを強みに、日本国内で業界をリードする国際見本市を企画、運営しています。また、メッセフランクフルト ジャパンでは、これからのライフスタイルマーケットを提案するインテリア・デザインのための国際見本市「インテリア ライフスタイル」を主催しております。
インテリアブランディングは、単なる空間演出ではなく、
ブランドの世界観を明確に伝え、顧客との関係性を深めるための重要な戦略のひとつです。
インテリア ライフスタイルでは、出展者の目的やブランド方針に応じたブース設計やプロモーション支援も行っています。
販路開拓や新規事業展開などにお困りの企業様は、まずは資料をご覧ください。